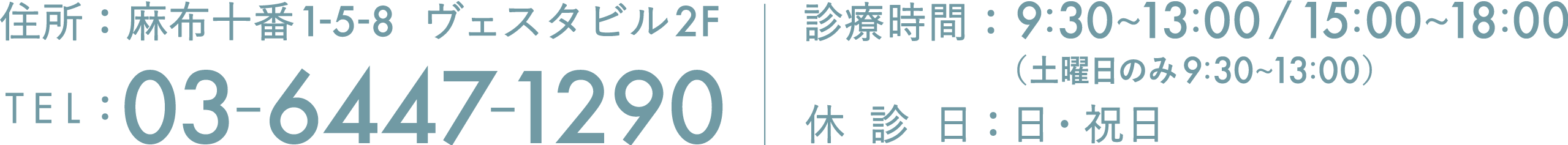<目次>
1.いぼ(疣贅/ゆうぜい)とは
2.いぼができる原因は?
3.いぼの診断は?
4.治療法は?
5.生活の中で気を付けることは?
1.いぼ(疣贅/ゆうぜい)とは
一般にいぼと言われているものには、皮膚の表面にできる小さな隆起性の病変で、ウイルスの感染による「ウイルス性疣贅(ゆうぜい)」や「扁平疣贅(へんぺいゆうぜい)」「伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ、=水いぼ)」、年齢とともに出てくる「脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)」、首や脇などにできる「軟性線維腫(なんせいせんいしゅ)」などがあります。さらにウイルス性疣贅の中でも多いタイプをまとめて「尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)」、そうでないものを特殊型と呼びます。いぼは部位や原因によってさまざま種類があり、顔や手足にできることが多いですが、全身のどこにでも発生する可能性があります。ここでは、もっとも多い「ウイルス性疣贅(尋常性疣贅)」について主に扱います。
2.いぼができる原因は?
(1)ウイルス性のいぼ
ウイルス性のいぼは、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染によって生じます。HPVは接触感染が主な感染経路であり、直接触ることによってうつるほか、タオルや靴、足拭きマットなどから間接的にうつることもあります。皮膚に小さな傷や肌荒れがあったり、お風呂上がりやプールの後で皮膚がふやけているとウイルスが侵入し、うつりやすくなります。ですので、調理などの仕事をされている方は、手が濡れていることが多く、皮膚の表面がふやけており、細かい傷も多いことから、HPVが侵入しやすく、手のいぼができやすいと言われています。同じように、アトピー性皮膚炎などで湿疹があったり、乾燥していたり、汗をかきやすい方も、皮膚のバリア機能が低下していて、うつりやすいと言われています。
□ 尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい):手足にできることが多く、表面がザラザラしています。痛みなどはないことが多いですが、足にできたものは大きくなると硬くなり、痛くなることがあります。
□ 扁平疣贅(へんぺいゆうぜい):顔や手の甲などに多く、平らで小さないぼ。
□ 伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ):いわゆる水いぼ。伝染性軟属腫ウイルスによるいぼで、子どもに多く、キラッとした小型のできものが体のどこにでもできます。
□ 尖圭(せんけい)コンジローマ:性器や肛門周囲にできるHPV感染症の一種。
(2)非ウイルス性のいぼ
ウイルス感染が原因ではないいぼもあり、特に加齢や摩擦、紫外線が関与します。
□ 脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう):年齢とともに生じる良性の皮膚腫瘍。紫外線に当たりやすい顔、手の甲などによくできます。サイズや個数などは個人差が大きいので、遺伝的な要素もあると言われています。
□ たこ(胼胝/べんち)・うおのめ(鶏眼/けいがん):圧迫や摩擦によって生じる角質の肥厚で、足の裏や足の指によくできます。ウイルス性いぼととてもよく似ていて、一見見分けがつかないことがあります。
3.いぼの診断は?
ウイルス性疣贅のほとんどが見た目で診断をつけることができますが、確実に診断するためにはダーモスコピー検査を行います。ダーモスコピー検査は、ダーモスコープという拡大鏡を使うことで、ウイルスによって増殖した毛細血管(点状出血)、皮膚表面の角質層の肥厚などを確認することができ、ウイルス性疣贅の診断にとても有用です。また、治療の効果の判定、治ったかどうかの診断にも使います。
また、職業や趣味、お子さんの場合は習い事をお聞きすることで診断の参考になることもあります。
以下の項目に当てはまるものがある方はウイルス性疣贅の可能性があります。ウイルス性疣贅は大きくなったり、数が多くなると治るまでに時間がかかることが多くなりますので、早めの受診をおすすめします。
□ 数mm~数cmの小さなできものがある。
□ 痛みなどの自覚症状はほとんどない(足は痛いことがある)。
□ 手、とくに指先や、足にできている。
□ 表面が硬くてザラザラしている。
□ よく見ると黒い点々がある。
4.治療法は?
いぼの種類や大きさ、数、また通院できる頻度、年齢などにより、適切な治療はかわってきます。当院では患者さまごとに最適な治療を検討、ご提案させていただきます。以下はウイルス性疣贅の治療についてです。
(1)冷凍凝固療法(液体窒素療法)
ウイルス性いぼの治療として最も一般的な方法です。液体窒素(マイナス196℃)をいぼに当てて組織を壊死させ、皮膚の再生を促します。ウイルス性いぼだけでなく、脂漏性角化症(しろうせいかくかしょう)や軟性線維腫(なんせいせんいしゅ)にも行うこともあります。日本皮膚科学会もウイルス性いぼに対してもっとも推奨している方法で、保険も適用されます。液体窒素療法はスプレーボトルで当てる方法、綿棒で当てる方法、またピンセットでつまみながら当てる方法があり、部位や大きさ、年齢などを考慮して適切な方法を選びます。少し痛みを伴うこともあり、過度に行うとやけどにつながる恐れもあるため、患部の状態に合わせて行います。液体窒素療法を行うと、通常、数日間周囲まで少し赤くなったり腫れたりした後、場合によっては水疱となってかさぶたとなり、剥がれます(手足のいぼはかさぶたにならないことが多いです)。通常、1度では取り切れないため、1~2週間ごとに複数回の処置が必要となります。とくに手足のいぼは治りにくいことが多く、数十回の治療が必要となることも珍しくありません。少し副作用がでるくらい強めに当てた方が治りが早いことが多いですが、痛みがつらかったり、何ヶ月も継続しても効果がない場合は他の治療への切り替えを検討してもよいでしょう。
その他の治療としては以下のようなものがあります。ウイルス性いぼの治療はさまざまなものがありますが、保険適応になっていないものが多いのが現状です。患者さんの年齢や背景、いぼのタイプや大きさ、数、部位などを考慮して、いくつかの治療を組み合わせて行うのが良いと思います。
(2)ヨクイニン内服
ヨクイニンはハトムギの主成分である漢方です。粒と粉があり、保険適応になっています。ヨクイニンを内服することで、免疫力を高めて治癒を早めますが、即効性はありませんので、継続して内服することが大切です。
(3) 外用薬 サリチル酸軟膏、スピール膏
皮膚表面の角質をふやかして、いぼを取り除きやすくします。手足などの硬くなっているいぼに保険適応になっています。
(4)レーザー治療
局所麻酔を行った上で、炭酸ガスレーザー(CO2レーザー)でいぼを焼き切る方法です。痛みやダウンタイムがありますが、液体窒素療法の通院が難しい方にはご提案することもあります。
(5)トリクロル酢酸塗布
トリクロル酢酸は強酸であり、いぼの組織を腐食させる働きがあります。痛みはほとんどないので、液体窒素療法が難しいお子さんや痛みに弱い方には良い適応です。液体窒素療法と同じように、1~2週間に一回、来院していただき、患部にトリクロル酢酸を塗り、乾かしたあとに絆創膏で保護をします。当日の入浴時は、まず患部を石けんで洗ったあとに、いつも通りに入浴をするようにしていただきます。トリクロル酢酸は強酸のため、粘膜(目・口・陰部)の近くや顔のいぼには使えません。
5.生活の中で気を付けることは?
□ ウイルス感染を防ぐ
まずはウイルスの存在を意識して、気を付けていきましょう。
傷口を清潔に保ちましょう:小さな傷からウイルスが侵入しやすいため、手洗いや消毒を徹底。
物の共有に気を付けましょう:タオルや靴、ネイル用品の共有を避けることが予防につながります。
適切なスキンケア:やさしく洗うこと、保湿をしっかりすることで正常な皮膚バリアが保てます。皮膚バリアが正常な皮膚はいぼがうつりづらくなります。
□ 免疫力を高める
本来、身体が持っている防御機能がウイルスの増殖や再発を抑える役割を果たしてくれます。
バランスの取れた食事をとりましょう。
十分な睡眠をとること、ストレス管理も大切です。
□ いぼを自分で削らない
無理に削るとウイルスが拡散し、別の場所に増えることがあります。
爪まわりにいぼがある場合は、専用の爪切りで爪を切るようにしましょう。ほかの部位と爪切りを共有するとうつることがあります。
ウイルス性いぼは自覚症状がないことも多く、気づかなかったり、病院を受診せずに様子をみていらっしゃる方も多いと思います。しかし放置すると一つ一つが大きくなったり、増えたりしますし、さらにご家族やご友人にうつる可能性もあるものです。いぼは大きくなると治療が長期間に及んでしまう可能性があるため、数が少なく、小さいうちに、早めにご相談いただくことをおすすめしております。根気が必要ですが、一緒に頑張って治療していきましょう。
参考)日本皮膚科学会ガイドライン 尋常性疣贅診療ガイドライン2019(第1版)