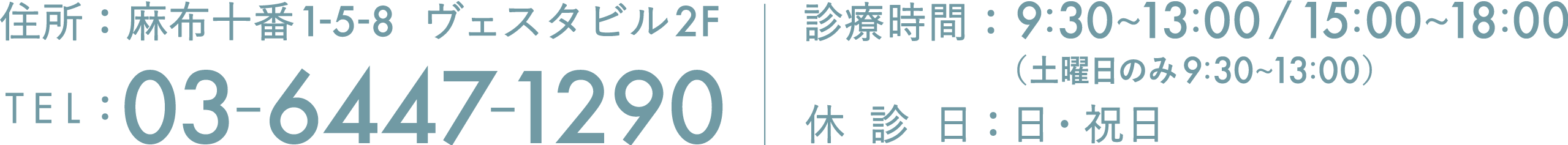<目次>
1.水虫とは?どう見分ける?
2.どうして水虫になるの?
3.水虫にも種類がある?
4.水虫の治療法は?
5.水虫は予防できる?
1.水虫とは?どう見分ける?
水虫とは、皮膚糸状菌(白癬菌)(はくせんきん)が皮膚や爪などに感染することで起こる皮膚疾患です。
●強いかゆみ
症状は足の裏や足の指の間の強いかゆみが特徴です。特に足に汗をかいて蒸れた時や、湿度の高い時期にかゆみが強くなることがあります。
●皮膚のはがれ、赤み
感染した部分が白くなってはがれたり、赤く炎症を起こすことがあります
●水疱(水ぶくれ)
足の裏や足の指の間に小さな水疱(水ぶくれ)ができることがあり、水疱が破れると痛みを感じることがあります。
●乾燥やひび割れ
特にかかとの部分で、乾燥し、ひび割れの症状がでることがあります。
●臭い
感染が進行すると真菌が繁殖し、皮膚の一部が腐敗することによって、強い臭いを発することがあります。
●爪が厚くなる
爪に水虫が感染した場合、爪が厚くなり、変色したり砕けやすくなることがあります。
2.どうして水虫になるの?
水虫の原因は白癬菌という菌です。この白癬菌は高温多湿の環境を好みます。手や身体にも感染することがありますが、特に足は靴を履くため蒸れやすく、白癬菌が繁殖しやすい環境と言えます。
水虫の人から白癬菌がついた皮膚が剥がれ落ち、その白癬菌がついたバスマットやスリッパなどを共有することによって感染します。
みんなが裸足で歩く場所、公衆浴場やプール、ジムなどといった施設のバスマット等には高確率で白癬菌がいると言われています。
ただし、白癬菌がついたバスマット等を使用したからといってすぐに感染するわけではありません。白癬菌が皮膚についたあと、そのまま24時間が経過してしまうと皮膚の角質層に白癬菌が侵入し、感染が成立することになります。
3.水虫にも種類がある?
水虫には様々な種類があります。
趾間型
足の指の間が白くふやけてじゅくじゅくしたり皮がむけたりします。
小水疱型
足裏の土踏まずや足のふちに小さな水疱(水ぶくれ)ができて時間がたつと赤くなって皮がむけます。
角質増殖型
足の裏やかかとが硬く厚くなり、カサカサして皮むけやひび割れを伴います。
その他、足の爪や手、体の他の部分に広がることがあります。
4.水虫の治療法は?
皮膚の表面を少しこすりとり、組織を顕微鏡で確認するとその場で水虫かどうかが判断できます。
水虫の治療には外用薬、内服薬が使われます。
(1)外用薬(塗り薬)
イミダゾール系(例: ケトコナゾール、ミコナゾール)
アリルアミン系(例: テルビナフィン、ナフトフィン)
外用薬は、患部に直接塗ることで真菌の増殖を抑える効果があります。軽度の水虫の場合は外用薬のみでも完治が可能です。
(2)内服薬(飲み薬)
テルビナフィン
イトラコナゾール
水虫が進行している場合や、外用薬だけでは治療が難しい場合に内服薬が処方されます。内服薬は全身に作用し、皮膚の奥深くにいる真菌にも効果を発揮します。
(3)市販薬
ドラッグストアなどでも水虫に効くクリームやスプレーも多く売られています。早期の水虫に有効な場合もあります。
水虫の治療には時間がかかることが多く、また途中でやめてしまうと再発することもあります。
完治するまでしっかりと薬を使い続けることが大切です。
5.水虫は予防できる?
水虫は一度かかると長い時間かかってしまうことがあるため、感染しないようにする工夫も大切です。
(1)「公共の場で裸足になったあとの一工夫」
大勢の人が出入りする公共の場でのスリッパ、マットには白癬菌が付着している可能性があります。とは言え、スリッパ、マットの使用はやむを得ない場合も多いですね。
そんな場合でも利用後に足の裏や指の間を石鹸などで洗うことで、白癬菌を洗い流すことができます。感染までは24時間以上かかるため、もし共有したとしても十分に予防は可能です。
(2)「患部をごしごし強く洗わないように気を付けましょう」
洗うことは大切ですが、ごしごしと強く洗ってしまうと皮膚を傷つけてしまい余計に感染してしまいやすくなってしまいます。
(3)「家族みんなで対策しましょう」
水虫の家族がいる場合、家庭内ではスリッパ、マットやタオルなどの共有をやめ、感染を広げないようにしましょう。